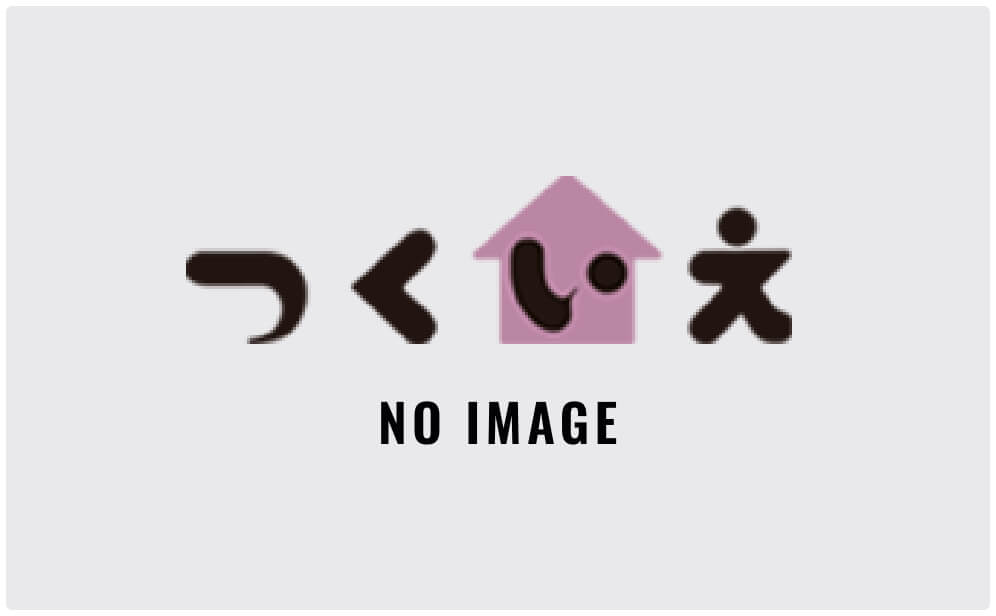

みなさんこんにちは!ツクキャリ運営事務局の上野です!
第2回キャリア説明会にご参加いただきありがとうございました!
グループディスカッション(GD)は就活では逃れられない過程です。しかし苦手意識が高い筑波大生が多いのが現状ではないでしょうか…。
そこで大手GD選考で9割の通過率を誇る私が、好印象を残すためのコツや企業の選考基準まで特別に教えちゃいます!!
最後には有名企業の実際に出題されたテーマも記載しているので、ぜひ最後までご覧ください!
目次
グループディスカッションとは?
グループディスカッションとは、4~10人の参加者がグループとなって1つのテーマについて話し合い、制限時間内で結論を導き出すもののことをいいます。大学で人と協業する経験がなかった人にはかなり厳しい試練だともいえます。
ではグループディスカッションってなんのためにやっているのでしょうか?企業側のメリットは主に2つあります。
選考の手間が省ける
企業はエントリーだけでも何千人もの学生を選考します。個人面談で1人に30分かけるより、GDを実施して30分で5.6人の選考を一気にした方が企業のコスパがいいのです。逆に言えば、目立てないと速攻落とされます。大人数の中で自分をどう見せたいか、戦略を立てて挑むことが大切です。
チームでワークをチェックできる
選考では主に個人面接が行われますが、実際にプロジェクトを進める上で重要なのは、個人のスキルだけでなくチーム内での協働スキルです。どれだけ経歴や人柄が良くても、チームワークに大きな欠陥があると「一緒に働きたくない」と思われ、選考で不利になる可能性があります。企業は個人としてもチームとしても優秀な人材を求めているため、両方のスキルを認められることが必要です。グループディスカッションでは、業務でのチームプレーを想定したスキルが評価されるのです。
基本的な手順
GDは好き勝手話せばいいというわけではありません。たいていの就活生はこの進め方の知識を入れた状態で挑んでいます。最初に議論においていかれないように、しっかり手順を覚えておきましょう!
1.役割分担/時間配分
2.前提確認
3.現状分析
4.解決策の発散/アイデア出し
5.解決策の収束/アイデアのまとめ
6.確定/発表
後に記載するテーマにもよりますが、基本的にはこの手順で進んでいきます。
「今これなにをやってる時間だっけ?」という意識は常に抱えておいて、議論がぶれていたら全体に共有してみるとウケがいいです。
主な役割
手順をすすめていくにあたって役割を決めることは必須です。チームで作業する際に必ずリーダーが誰か決まっていたりしますよね。GDでも役割を決める必要がありますが、開始1分でさらっと決まってしまいます。つまり役職は早いもんがちです。企業側に自分の能力をアピールする場面として、ふさわしい役職を勝ち取っておくこともGDを勝ち抜くコツです!
以下に主な役割と、評価されているポイントと所持していたら向いているスキルを紹介します。ぜひ自己分析して自分に適した役職をみつけてください!
ファシリテーター
ファシリテーターは、一言でいえばグループの司会の役割を担います。ディスカッションの進行を行い、参加者の意見をうまく引き出します。司会は目立つので評価が高いと思う人もいますが、冷静な判断力や会話の流れを読む力も必要なため、やや難易度が高いポジションともいえます。コミュニケーション能力や積極性はもちろん必要ですが、他人に気配りができる人が向いているとも言えます。ファシリが下手だとグループ全体の評価が悪くなることにもなるので初心者は安易に挑戦するのは控えたほうがいいかもしれません。
評価されるポイント
・どういう流れで議論を進めるかをわかりやすく示せるか
・論理的な思考力があるか
・自分以外の役割を理解し、それぞれの意見を引き出せているか
・意見をまとめられるか
・目立つことが目的になっていないか
向いているスキル
・リーダーシップ
・全体を俯瞰する力
・傾聴力
・臨機応変に対応する力
書記
書紀は、話し合いの要点を書き残し、最後の発表に向けてわかりやすくまとめていく役割です。誰でも簡単にこなせる役割の一つですが、役職を持ったことに安心して会話に参加しないのはNGです。文章をまとめながら共通点を見つけ出し議論を活発化させる必要があるので、マルチタスクが苦手な人には向かないかもしれません。そのため書紀は意見をまとめるのがうまい人に特におすすめです。話の内容を体系的に理解して整理するのが得意な人は進んで立候補しましょう!
評価されるポイント
・要点を取りこぼさずメモできているか
・発表がスムーズになるような内容でまとめられているか
・内容が理解できないときなどに適宜、会話に参加して確認できているか
向いているスキル
・聞き取り、文章化スキル
・タイピングスキル
・論理的思考力
タイムキーパー
タイムキーパーは、時間内に議論を進め、発表内容をまとめるためにタイムコントロールをする役割です。議論が白熱してくるとつい時間を忘れてしまいがちですが、時間内に仕事を完了するスキルは社会人にとって重要なものです。
ただ時間を読み上げるだけでなく、ディスカッションの流れによって時間配分を変えて、臨機応変に対応できると評価が上がることも。ただ書紀同様、それだけをやっていても意味がないので、他の役職と兼任するようにしましょう。
評価されるポイント
・時間内に問題なく議論が進むよう管理できているか
・議論の展開状況に合わせて、うまく時間配分を変えられているか
・時間管理をしながら、ほかの役割のサポートや積極的な意見出しをしているか
発表者
発表者は、GDをで話し合った内容を、採用担当者やほかのグループの前で発表する役割です。書記がまとめた内容をただ読み上げるだけでなく、自分なりの言葉で、抑揚をつけて話すスキルが求められます。物怖じしない性格や、人前で話すことに慣れている人におすすめ。プレゼン慣れして、我こそはというひとはぜひ立候補をしましょう!そして発表者がしっかり話に参加していることは当たり前です!最後にみんなで議論した重要なポイントを逃さず発表して協調性をアピールしましょう!
評価されるポイント
・立ち居ふるまい、話し方や表情など
・大勢の人の前で話す度胸があるか
・瞬時に議論をまとめてわかりやすく説明できるか
向いているスキル
・プレゼンテーション能力
・瞬時に議論をまとめる頭の回転の速さ
アイデア出し
アイデア出しは、名前の通り議論が活性化するように、さまざまな角度からアイデアを出す役割です。基本的に上記の役職につけなかった人は必然的にアイデア出しになります。役職につけなかったからといって落ち込むことはありません!アイデア出しとして数多くテンポよくアイデアを出しましょう。ただ空気を読まずに発言しすぎるとクラッシャーとして扱われる可能性もあるので、気をつけましょう笑。
評価されるポイント
・多角的な視点で意見を出せているか
・積極的に話を切り出して、場の空気をあたためているか
・テーマからずれた発言をしていないか
向いているスキル
・アイデアマン
・さまざまな角度から積極的に発言できる能力
企業が見ているポイントとは?
チームワークを見ているといっても具体的にどんなスキルを評価しているのでしょうか?GDで「このポイントを抑えておけば大丈夫!」という4つをご紹介します!
協調性
異なる考えや意見を持つチームメンバーと1つの解決策や回答を導き出すための協調性も評価をされます。
ディスカッションでは、必ず意見の違いや衝突が発生をするものです。
自身の意見ばかりを主張していては、チームとしての解決策や回答がまとまらず時間を浪費してしまうことになります。
GDでは、自身の意見を述べながらも、他のチームメンバーとすり合わせをしながら、1つの回答を導き出す協調性が重要であり、企業も評価をしている点を押さえておきましょう。
コミュニケーション能力
コミュニケーション能力について評価をしている企業が多く、チームでの発言を見られています。
いかに自身の意見を提案するか、議論をどのようにまとめていくかなど、チーム内での発言・姿勢が評価のポイントとなります。
発想力
結論にどこまでジャンプがあるのか、評価している企業も多いです。奇天烈な発言をするのではなく、「なぜそれが効果的なのか」の論理性をもたせた発言をする必要があります。面白く的確なアイデアを出せる人は、新しい挑戦の姿勢を掲げる企業にかなり評価が高くなるでしょう。
論理的思考力
他者に物事を整理しながら分かりやすく伝えられる論理的思考力についても評価をされています。物事を構造立てて丁寧に伝えられる能力は、議論を遠隔に進めるためにも活きる能力です。
自身の考えを「結論」から伝え、短く分かりやすく伝えられる能力は高く評価をされます。
論理的思考力は、すぐに身に付けられるものではないので、日々のニュースや時事問題について、意見を短文でまとめるトレーニングなどを積んでおくことをおすすめします。
通過率99%!?立ち回りの裏技
実はGDの立ち回りにも裏技があります!前途した役職をこなすのは大前提で、この発言をしたら大逆転の可能性あり!?な裏技を特別に教えちゃいます!
私の周りでGD無双している友達はこの3つのどれかを意識しているので、効果は抜群です!まずは難易度の低い順から試してみてくださいね。
話していない人に降る(難易度C)
グループの中には話すのが苦手だったり、勢いに負けて一言も話せていない学生がいることがあります。そんなときに切り捨てるのではなく、誰かの意見に同調しつつ「たしかに、いいですね。〇〇さんはどう考えていますか?」というように話を振ってあげましょう。このときのポイントは急に意見を投げるのではなく、誰かの意見に対してどう思うか、を投げてあげることです。Howではなくyes/noで答えられるような簡単な質問にしてあげると、話が苦手な子でも会話に参加しやすくなります。私の場合、振って出た意見はなるべく話の大枠の一つに入れてあげるようにしていました。そうすることで、話せていない子がチームに貢献した構図も作れるし、ちゃっかり協調性の面で自分のポイント稼ぎもできちゃうんです笑
話の軸を戻す/話題を集約する(難易度B)
これはかなり多くの人が行っていて、あまり労力を使わないのに評価が高くなる禁断の裏技です。具体的には、全体像を掴みながら議論を前に進めていく発言をすることです。
「話の軸を戻す」とは最初に決めた定義とはズレた議論をしていたり、論理性を担保するに足りない議論を促したりすることです。次に「話題を集約する」とはAさんとBさんの意見の共通点をまとめて、意見の収束を促す発言のことです。「この意見とこの意見ってつまりこういうことですよね。この方向で進めていけそうじゃないですか?」というような感じです。これは誰かしら意見が出ていればできる技なのでだいぶ労力少なくできます笑
全体像を把握しながら、議論の説得性を上げられる重要な役割で、誰も気づかなかったことに気づいた調整力を評価してもらえます。
根幹となるアイデアを出す(難易度A)
これはかなり難易度が高く、アイデア出しの役割の中でも論理性があって新しい発想ができる人は挑戦する甲斐ありです。アイデア出しって結構平行線になりがちで、斬新なアイデアを出せる人ってなかなかいません。そんなときに「こんなのどうですか?」とグループ全員が共感できるアイデアを出せると、話の結論はすべてあなたが主軸になります。正直それまであまり目立っていなかったとしても、鶴の一声に影響力があると判断され、かなり逆転の好評価が期待できます。
ただやはり完璧なアイデアを出すことは容易なことではないので、常にアイデアが斬新で納得できるものを出そう!と意識しておくくらいでも十分かなと思います。
よくある失敗パターンとその回避方法
初心者でGD完璧な人なんていません!ここで最初に陥りがちな失敗を学んでおけば、ダメージを最小に抑えられるかもしれません!しっかり頭に入れておいて下さい。
時間切れ
これにはいくつか原因がありますが、時間配分どおりに議論が進んでいないことが原因なのがほとんどです。はじめにタイムキーパーのそもそも時間配分に無理があったり、話の脱線が多くて話がまとまっていなかったりと、初めてGDをする人が多いと最後にあたふたして直前に出た適当なアイデアを発表してしまいます。それではとてももったいないです!
回避方法としては①タイムキーパーが「残り〇〇分だからそろそろ決めよう」など話の収束を促す発言をする②タイムキーパー以外は「あと何分だっけ?」など時間を常に気にしながら会話をする。
この根本的原因は全員に時間を守ろうとする意識が足りないこと。タイムキーパーだけでなく全員が、話を遮ってでも時間配分を意識させる発言をすることが重要です。
否定ばかり
よくいうクラッシャーの部類の一つです。出た意見に対して毎回否定ばっかり。ひろゆきさんに憧れてるのか論破大会と勘違いしている人ってたまに見かけるんですよね…GDは意見の勝ち負けではなくチームで協力して答えを出すことが目的なことを忘れないで下さい。回避方法としては、「なるほどだしかに、こういう要素をいれたらもっと良くなると思う」というように、その意見がもっと良くなるためのエッセンスを足してあげるようなイメージで発言すると、相手も嫌な感じはしなくなります。
自分がクラッシャーに巻き込まれる場合もあります。そうなると共倒れになってグループ全員不通過になってしまうこともあります。回避方法としては、批判に対して「なぜそう思うのか」「では、あなたはどうするのが良いと思うのか」と意見を出すことを促しましょう。そうすることにより、否定タイプの人もただ闇雲にほかの人の意見を批判できなくなるでしょう。
存在感が薄い
オンラインのGDが増えると声が重なって会話に入りにくくなることがあります。そもそもしゃべらないのは論外ですが、目立った意見が言えずニコニコ同調しているだけなのも、スキルが伝わらず不通過になります。存在感や自分のスキルをアピールするためには、多少の積極性は必要不可欠です。会話が苦手だからと逃げちゃだめです。
回避方法は簡単な役職(タイムキーパーor書紀)をやるか、積極的にアイデアを出すことです。本当に会話が苦手であれば何かしら役職をやっていれば少しは積極性がプラスされます。ただそこからポイントを稼ぐには発言量を増やすしかありません。場数を踏んで慣れていくことで克服できるので、ゆっくり練習していきましょう。
論理性や具体性の欠如
最後まで結論がだせたけど、意見がいつもありきたり…なんてことありませんか?
この失敗パターンはプラスアルファGDのスキルを挙げたい人に意識してほしいことです。回答までのロジックが欠けていると、議論はいいけど結論が弱く見えます。会社では結局結果がすべてです。説得力のある意見にするには短い時間で、論理性や具体性を追求してみてください。
回避方法としては、結論を出す前に自分の中で一度話を振り返ってみて下さい。冷静に客観視して、「ここの部分の根拠が弱いんで、もう少し議論しませんか」などと声をかけることでグループの意見がさらに強固になるでしょう。
グルディステーマの種類
GDには大きくわけて5つのテーマに分類されます。1つずつ見ていきましょう。
抽象的テーマ型
抽象的なテーマを議題に学生が1つの答えを出すタイプのGDです。テーマが抽象的で誰しもが自分の意見を持ちやすいからか、それぞれの意見が交錯し答えが出ずに終わる、なんてことが頻発しがちなのがこのタイプです。
前提確認をしっかりしてから収束発散に向かっていきましょう。
例:「理想の職業」とは何かについて
課題解決型
与えられた課題について、解決策を提示することを目的としたタイプのGDです。簡単な資料がある場合とない場合があります。よく出題されるテーマは、以下の3種類です。
・「企業に関連するテーマ」
・「時事に関するテーマ(ex:老人用SNSを普及させるには?)」
・「なじみのないテーマ」
この場合、いきなりビジネスプランを考えようとしないで、定義づけ→現状確認の工程をしっかり踏むことが大切です。
例:(企業のサービス)の売上を伸ばすためには?
資料分析型
与えられた資料を読み解き、最善と思われる解決策を提示するGDです。
課題の解決という点で、課題解決型GDと似ていますが、意見の根拠が資料、または資料から類推された事実に限るという点がポイントです。事実ベースで議論を進めなければならず、GDを始める前に、個人ワークの時間が設けられる場合もあります。このタイプのGDは長丁場の勝負となることが多いです。「前提確認→現状分析→原因特定→アイデア出し→アイデア吟味→結論」という進め方を進めましょう。この6つのプロセスのうち、どれか1つでも抜けているとマイナス評価につながる可能性があります。どのGDよりも結論が重要視されるのが、このテーマです。
例:今年どのような柔軟剤を出すべきか(資料あり)
ディベート型
反対/賛成の立場、または自分に明確な役割が与えられた上でテーマについて議論するGDです。反対/賛成の2つの立場に分かれる場合、資料はありませんが、学生それぞれに異なる役割が与えられた場合は、自分の役割、状況が書かれた資料を渡されるケースが多いです。
この種類のGDにおいて大切なのは、「初めに判断の基準を作る」ことです。
自分の立場が決められた状態でGDが始まるため、「自己主張の押し付け合い」になりやすい形式です。けんかを避け、議論を成り立たせるため、判断の基準を設定することから始めましょう。
例:就活にESは必要か
フェルミ推定型
フェルミ推定とは、実際に調査することが難しい数量や規模を、最低限の知識と論理的思考力を使って短時間で推定する手法です。 例えば「日本にある電柱の数」など一見予想がつかない数値を、国土面積や身近にある電柱の数などから論理的に推定します。日常生活からビジネスまで幅広い場面で応用され、採用試験ではコンサルティングファームや投資銀行、総合商社などで多く出題されます。
かなり難しいですし、導入している企業も限られているので、範囲外の業界であれば対策は不要です。
例:日本にはマンホールがいくつあるか
有名企業過去GDテーマ
では実際のGDのテーマにはどんなものがあるのでしょうか。
一覧にしてみたので、気になる企業があればぜひ練習してみましょう!
GDテーマ
・北海道にある鉄道会社の売上向上施策を提案してください(アクセンチュア)
・電気自動車を普及させるために必要なことを、技術的、マーケティング的側面か ら教えてください(トヨタ自動車株式会社)
・21世紀を代表する企業に必要な要素はなにか(サイバーエージェント)
・みずほが今後投資すべき事業(株式会社みずほ銀行)
・リーダーが果たす役割とは(PwCコンサルティング合同会社)
・海外の森林を用いた新たなビッグビジネスとなる企画を考えてください。(三井物産株式会社)
・学生と社会人の違いは(野村證券株式会社)
・学校の授業に新しく取り入れるべき教科について(楽天グループ株式会社)
・子どもにスマートフォンを持たせるべきか、もし持たせるのであれば何歳からが妥当か(ソフトバンク株式会社)
・5人の異なった候補者のうち、誰を新規リーダーに採用するか(アステラス製薬株式会社)
・あなたがしてきたスポーツを世界レベルに引き上げるためにはどうすればよいか(三菱商事)
・日本で1日に消費される卵の数を求めよ(ボストンコンサルティンググループ)
今からできる対策方法
ここまでで、GDのおおまかな内容やコツを把握できたと思います。では実際の選考に勝つためにはもう一歩対策が必要です!
具体的に私が就活中に行っていたGD対策方法を特別にお教えします!
実践動画をみる
YouTubeで「グループディスカッション 対策」と検索すると、実際に学生がGDを行っている動画がたくさん出てきます。その動画を見て雰囲気を掴んだりや流れを把握することも大事ですが、私は「自分だったらどんな立場になるかな?」「どんな発言をするかな?」と考えながらみると、どんどんちからがついていきます!また、動画だけじゃなくコメント欄も見てみると一般的に良い立ち回りと悪い立ち回りがわかっておもしろいですよ笑
以下におすすめの動画リンクを貼っておくので、ぜひ試してみてくださいね🙌
https://youtu.be/MvBrJOJv2N8?si=NtobQkiu0Zs8SsjR
https://youtu.be/4_UhXP2jx_s?si=6I_y2c-Ao3n4DPoX
https://youtu.be/ISLnnqDn-DM?si=WPOZENw9f6Iwh-jt
小さい企業の選考で練習
GDは場数を踏むことも重要です。学校で実施するグループワークと同じようなスタンスでやっていると、うまくいかないのが就活のグループディスカッションです。
場慣れするためには、何回も練習をするしかありません。そのために私の場合は、志望度が高くないがGD選考のあるベンチャー企業を見つけて、10社ほどGDの経験を積むためにエントリーしていました笑 もちろんそこで「いいな」と思う企業であればそのまま選考に進めばいいですし、面接対策する時間が勿体無いと思うのであれば(あんまり良くないですが)最悪選考辞退すれば大丈夫です。
GD練習イベントに参加する
企業でのGD選考はハードルが高いという人には、GD練習イベントに参加することがおすすめです。筑波大のキャリア支援や就活支援団体のイベントももちろんありますが、私はあまりおすすめしません。過去に参加しましたが、特にコツの解説もないまま「はいどーぞ!」という流れでサクッと終了してしまい、なんだか時間の無駄だったなと、それ以降一度も参加していません。なぜこんなことになるかというと、GDが得意な人が仕切っているわけではないからです。学生団体は所詮最近就活を終えた学生ですし、キャリア支援はただの大学職員なので、GDの知識が十分にあるわけではありません。そのためこれらに参加してもただの場数稼ぎにしかならないのです。
そこでおすすめするのがツクキャリです!ツクキャリでは、就活無双していた筑波大OBによるディスカッションのコツ徹底解説から、実践を通じたアウトプットをすることができます。さらに企業の人事に実際の採用基準と照らし合わせて個人的フィードバックをもらえるなど、1回の参加で必ずスキルが定着できるコンテンツが用意されています。知識の吸収から企業の選考案内まで一括でできるのは、ツクキャリだけ!すべて無料で利用できるので、金欠な筑波大生には嬉しいポイントですね笑
就活相談ならツクキャリ!
ツクキャリでは筑波大生専門で就活支援サービスを行っています!
月1回のイベントでは人気企業がつくばまで来て登壇し、特別選考やここでしか聞けない選考情報が盛りだくさん!
ツクキャリで一緒に第一志望内定を目指しましょう!
▼▼▼個別相談ツクキャリLINE登録はこちら▼▼▼
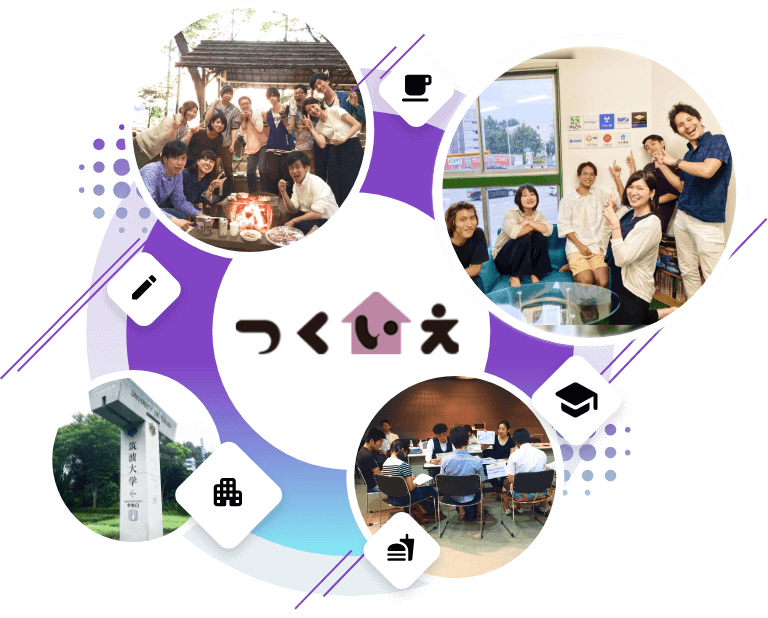
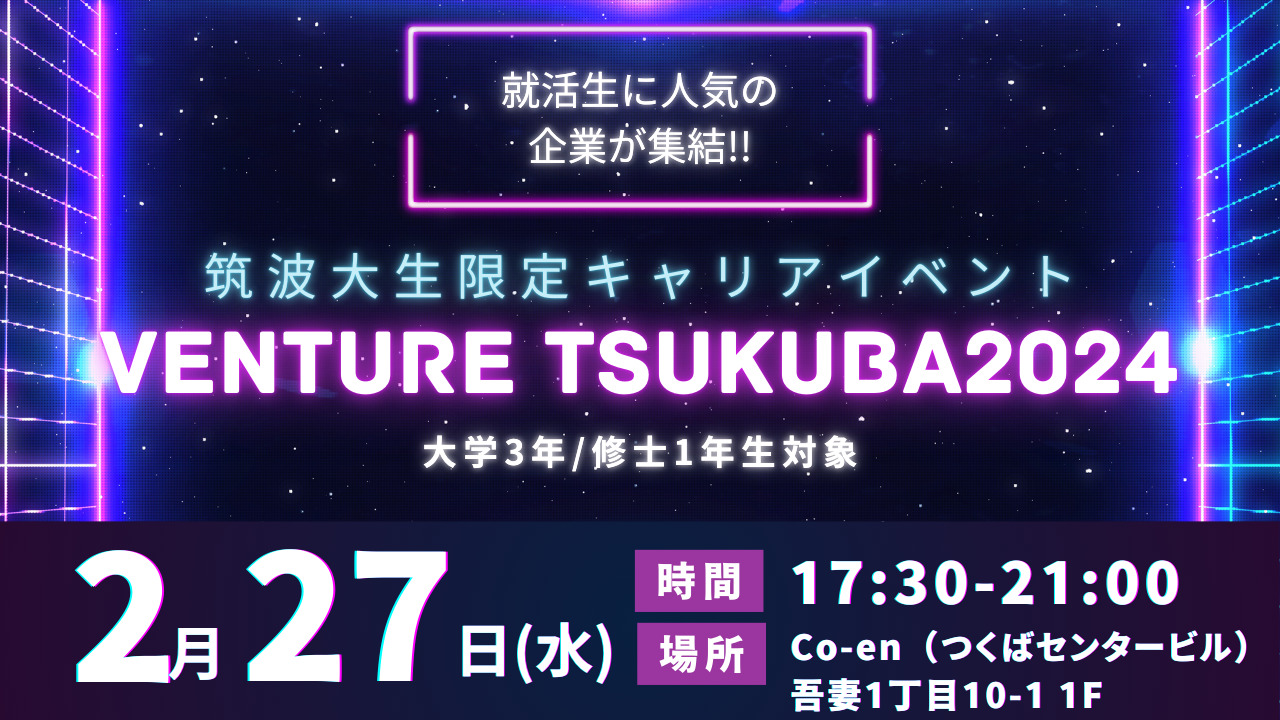

コメント